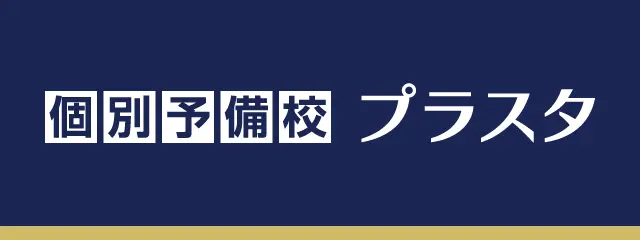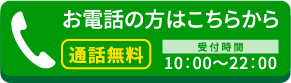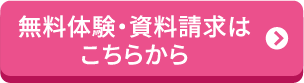節分で豆まきする理由?起源や鬼の由来を知ろう

こんにちは!オンライン家庭教師WAMです(^^)/
みなさんも節分になると豆まきをしたことがあると思います。
子どもの頃、お父さんやお母さんに鬼のお面かぶってもらい
「鬼はそと・福はうち」と、豆をおもいっきり投げつけたという経験があるのではないでしょうか。
この当たり前のようにやってきた豆まきですが、
「どうして豆まきをするの?」と思ったことはないですか。
今回は、節分で豆まきをする理由や起源、鬼の由来などを紹介していきます!
Contents
節分って?いったい何
節分は各季節の始まりの日の前日を指します。
立春・立夏・立秋・立冬の前日はすべて節分というのですが、特に江戸時代以降、旧暦の新年と重なる立春(2月4日頃)を節分として重要視されるようになりました。
豆まきをする理由は、季節の変わり目には邪気(鬼)が生まれると信じられていて、それを追い払うための儀式とされていたからです。
●●●豆知識●●●
知っていましたか?豆まきは日本古来の風習で、
2020年までは2月3日が節分でしたが、2021年は2月2日に変わります。
2021年~2057年まで、4で割り切れる年は3日。4で割って1余る年は2日が節分です!
節分で豆まきをする理由?
豆まきは、室町時代の看聞日記に「抑鬼大豆打事、近年重有朝臣無何打之」とあることから、すでに宮中や都の公家の内では豆まきが行われていた記録もあり、古くから行われてきた儀式といわれています。
元来、中国から伝わったとされ「追儺(ついな)」「鬼払い」のという災いを祓う儀式がもとになっています。
豆・穀物には生命力と魔除けの呪力が備わっているとされていたこともあり、「魔目(豆・まめ)」を鬼の目にぶつけることで鬼を滅し邪気(鬼)を払い無病息災を願うとされてきました。
魔(鬼)を滅する「魔滅」からマメになったとされています。

豆ならなんでもいいの?
ほとんどの地域では「大豆」を使いますが、北海道・東北・北陸などのおおよそ8割と、鹿児島や宮崎の一部はピーナッツ(落花生)をまくそうです。
大豆は五穀(米・豆・麦・粟・ひえ)と言い、農耕民族である日本人には欠かすことのできない食べ物です。
豆をまくところが多数ですが昔は米・麦・粟・炭なども使われていました。
米・豆は神聖なものとされ、特に豆は粒が一番大きく悪霊を追い祓うには最適とされたからです。
ピーナッツ(落花生)をまくのは粒が大きく拾いやすく皮がついていて地面に落ちても汚れないのが理由のようです。
豆をまくのに正しい方法はあるの?
豆をまく方法はいろいろあります。
神社や地域によっては餅・みかん・お菓子などを投げるところもありますが、ご家庭でやる豆まきが代表的です。
ここでは一般的な方法を紹介します。
①福豆を用意します
福豆は炒った大豆のことを言います。
生を使わず炒ったものを使うのかというと拾い忘れた豆から芽がでてしまうと縁起が悪いとされたためです。
まず福豆を用意してください。
②夜まで待つ
鬼は丑寅の刻(真夜中)に来るのでみんなで待ちましょう。
ここでお面を用意するのも忘れないでくださいね。
③豆をまく
一般的に一家の家長の役目ですが、現在は年男・年女・厄年の人がまくと縁起がいいとされていて、地域によっては小学校6年生が中心になって行う地域もあります。
「鬼はそと」「福はうち」の掛け声で
奥の部屋から順番に戸や窓を開け外にむかい「鬼は~そと」、戸や窓を閉め中に向かって「福は~うち」と玄関に向かってまきます。
順番や方向などは地域により違いますが大きな声でまきましょう。
④豆を食べる
1年の厄除けを願い自分の年齢より1つ多く豆「年取り豆」を食べます。
地域によっては1つ多く食べると体が強くなり、風邪を引かないなんて言うところもあります。
節分でイワシの頭を飾る理由は
節分というと豆まきを思い浮かべますが、玄関先に柊の小枝にイワシの頭を刺し飾ってあるのを目にすることもあります。
これは西日本に多い風習で「柊鰯(ヒイラギイワシ)」と呼ばれます。
臭さがきついものは魔・厄を寄せ付けないと言われ、焼くと臭さがきつくなるイワシを飾り厄除けしたと考えられています。
また、あえて食することで「陰の気を消す」として西日本では節分の日によく食べられます。
「鬼は外」「福は内」の掛け声の意味はあるのかな
豆まきの際に行う声掛けですが、魔・厄を追い払うために「鬼はそと」、邪気がなくなったら福を招き入れるために「福はうち」と声をかけます。
「鬼は外」「福は内」の順番で声をかけるのが一般的です。
一部の宗教上、鬼を神とする地域や鬼がつく姓が多い地域では「鬼はうち」「福はうち」とも言い、また鬼がつく地名の多い地域では「福はうち」「鬼もうち」と言う地域もあります。
茨城県のつくば市鬼ヶ窪では、「あっちはあっち、こっちはこっち 鬼ヶ窪の年越しだ」と声がかかるそうです。
はてさて、鬼はどこから来たの?
そもそも、鬼って本当に存在するの?
鬼は人間の心に潜む恨みや憎しみが作りだしたもので、もともと形なく目に見えない隠形(おんぎょう)のおんがオニに変化したものとされています。
中国では死んだ人の魂のことでした。
今の鬼のイメージは日本古来からの仏教が影響しています。
仏教でイメージされるのが地獄の番人、罪を犯した囚人を見張っている係のこと。
地獄とは自分が生み出した苦しみのことで欲・怒り・愚痴の心のたとえにされてきたのです。

鬼の色は意味があるの?
鬼の色には意味があります。
鬼の色は仏教「五蓋(ごがい)」に由来し、仏教の瞑想修行を邪魔する煩悩と関係があります。
- 黒鬼(ぎ・疑) / 黒・・・愚痴
- 白鬼(じょうこ・掉挙 おさ・悪作) / 白・・・後悔
- 赤鬼(どんよく・貪欲) / 赤・・・欲望
- 青鬼(しんに・瞋恚) / 青・・・怒り・憎しみ
- 緑鬼(こんちん・惛沈 すいみん・睡眠) / 緑・・・倦怠
を意味しています。
人の心に住む「負」の感情そのものが色で表現されています。
なぜ鬼は嫌われる存在なのか?
鬼と言えば 頭に角があり、口に牙がはえ、爪が鋭くのびた大男を想像します。
中世の能楽では、鬼は人の怨霊化した地獄のものとされ、悪者にされてきました。
そのころから悪者のイメージがついたようです。
平安時代になると、人に危害をあたえ人を食ってしまうという存在となり、人に化けて人を襲う、人が憎しみの念が満ちて鬼に変化する、般若の面のように嫉妬心に負け女性が変化するというお話が伝わっていきます。
以降、多くの昔話の中に出てくるほとんどの鬼は人を襲ったり、人を食べてしまう残酷なものになっていきました。
徐々に恐ろしいものへと変貌していったのです。
現在においては、悪いもの・恐ろしいものの代名詞として使われるようになりました。
いい鬼もいるのです!
身の回りの生き物にオニがついているものもいます。
ひときわ大きいものにオニってつけ呼んでいるのです。
- オニヤンマ(とんぼ)
- オニヒトデ(ひとで)
- オニユリ(花)
人とは思われないほどの才能のこともオニとよんでいます。
〇〇のオニ のような使われ方をします。
- 仕事のオニ
- 野球のオニなど
力強い・超人的といったイメージです。
嫌われる役回りばかりではないのです。
例えば
- 「なまはげ」 家を回って厄払いをする鬼です。
- 「鬼子母神」 子供の守り神です。
- 「鬼鎮神社」 関東唯一の鬼を祀る神社です。
人々に信仰されて祀られていった鬼もあり、いい鬼の伝説も残っています。
いろんな鬼が出てくるお祭り
全国津々浦々、無病息災を願う鬼が出てくるお祭りはたくさんあります。
代表的なものをいくつか紹介します。
- 「うわじま牛鬼まつり」 全長約5mの牛鬼が練り歩くド迫力 宇和島市>愛媛県
- 「大善寺玉垂宮の鬼夜」 日本3大火祭りのひとつ 久留米市>福岡県
- 「陀々堂の鬼走り」 父・母・子鬼が燃え盛る松明を振り返りかざす 五條市>奈良県
- 「廬山寺の鬼法楽」 3色(赤・黒・緑)の鬼がかわいらしい 京都市>京都府
- 「滝山寺鬼祭り」 800年つづく火祭り 岡崎市>愛知県
- 「登別地獄まつり」 鬼をかたどった大きな山車が見どころ 登別市>北海道
- 「大宝の砂打ち」 見物客や子供に砂を投げる変わったお祭り 五島市>長崎県
- 「古式追儺(ついな)式」 鬼に豆をまかないで頭をなでてもらうお祭り 神戸市>兵庫県
- 「豊橋の鬼祭り」 白い粉とたんきり飴で厄除け みんな真っ白 豊橋市>愛知県
- 「水津の夜祭」 鬼太鼓の乱れうちです 佐渡島>新潟県
すべて歴史も古く今もなお全国で行われています。
火を使う火祭りが多く結構ド迫力です。
地域で変わる節分の風習
節分と言えば豆まきですが、恵方巻も忘れられません。
最近は、恵方巻き(太巻き寿司)を丸かぶりする方も増えてきています。
恵方巻は、江戸末期に大阪船場で商売繁盛を祈願する風習から始まり、1970年代に大阪道頓堀で行ったイベントで復活。
1990年代に一部コンビニで全国展開し宣伝されたことで、ここ20年で一気に広まっていきました。
ちなみに、恵方巻きという名前はセブン・イレブンの商品開発で作られた名前だそうです。
恵方とはその年の福徳を司り、それに向け物事を行えば何事も吉とされている方向です。
恵方巻きの起源・発祥については諸説あり定かではありませんが、大阪花街で働く女性たちがお正月である節分日に歳徳神さまにお願いしながらお寿司を食べたことが由来とも言われています。
恵方巻きを食べるときは、その年の恵方の方向に身体を向け、丸々一本を途中で休むことなく一気に食べ進めます。
当然おしゃべり禁止ですのでご注意ください!

その他、こんな風習がある地域もあります。
福茶(ふくちゃ)
豆まきの際に歳の数だけ食べられないときに、豆を入れたお茶を飲むという風習もあります。
福茶は豆・昆布・梅を入れた京都・六波羅蜜寺の「皇福茶」が有名で
〇豆3粒(縁起のいい吉数でまめまめ働ける) 〇昆布(よろこぶ) 〇梅(松竹梅)
の意味がありとても美味しくいただけます。
こんにゃく
節分に四国をはじめとする各地で食べられています。
身体にたまった砂を出すと言われ「砂おろし」とされる風習です。
身を清めるという意味もあるのだそうです。
くじら
イワシとは異なり大きなクジラを食べることで心や志を大きく持つとして、山口県の一部で節分に食べられています。
大きなクジラはえさを丸のみするので邪気も丸のみしてもらおうと言うところから来ています。
他にも・節分そば(山陰地方)・けんちん汁(関東地方)などもあります。
まとめ
いかがでしたか?
冬の代表的な行事として定着している「豆まき」は、家族のイベントとして毎年行っているご家庭も多いかと思います。
本来の豆まきのルーツを知ることで、今までとは一味違った風習などが体感できるはず。
長さ24.5cm×幅8cm×高さ5㎝のサイズの恵方巻きロールケーキなども市販されています。
ぜひ「豆まき」に、小さい子どもたちと一緒にいろんな行事食も食べて楽しくお過ごしください!







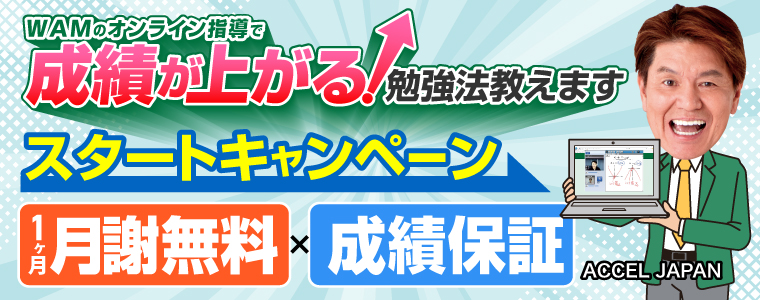

 0120-333-876
0120-333-876