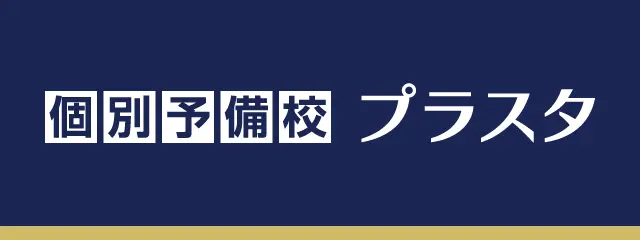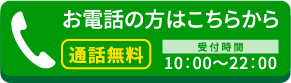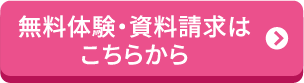勉強がはかどる!集中力を高める方法

こんにちは!オンライン家庭教師WAMです(^^)/
早速ですが皆さんは、勉強をしなければならないことは分かっているのに、「集中できずにできなかった」「集中が続かず時間がかかってしまった」などという経験はありませんか?
人間の脳は指示があったからといって、集中できなければ正確に実行できるわけではありません。
今回は、集中しているときの脳のしくみや集中力の高め方をご紹介します!
Contents
そもそも集中力とは何か?

集中力とは?
集中力とは、「一つの事柄に集中して物事に取り組む能力」のことを指しています。
勉強に限らず、スポーツなどにも集中力は必要不可欠であり、どれだけ高い集中力を保てるかが物事の成否に大きく影響するといっても過言ではありません。
集中力のメカニズム
集中するためには、まず脳の仕組みを知ることが大切です。
脳には、3つの情報処理ネットワークがあります。
それぞれがどのような機能を果たすのか、「自宅から、通い慣れている学校へ行くまでの道のり」を例にして紹介します。
①デフォルトモード・ネットワーク
皆さんは通い慣れた通学路を歩く時、“常に”注意を払って歩いているでしょうか。
実際は、何か考え事をしていたり、何も考えずにぼーっと歩いていても、学校には問題なく行けることでしょう。
この時の脳は、『デフォルトモード・ネットワーク』が働いており、無意識に近い状態でも、過去の記憶や経験から自動的に「学校へ向かう」という指示が出されているのです。
②セントラル・エグゼクティブ・ネットワーク
続いて、通学路の途中で自動車の交通量が多い交差点があったとします。
その時、皆さんはたとえ毎日通っている道でも、事故に遭わないように注意して通るのではないでしょうか。
脳はこの瞬間、『セントラル・エグゼクティブ・ネットワーク』へと切り替わり、自発的に意識を向け、注意をするようになります。
つまり「集中する」ということは、脳がセントラル・エグゼクティブ・ネットワークの機能を果たしている瞬間であるといえるでしょう。
③サリエンス・ネットワーク
最後に紹介する『サリエンス・ネットワーク』は、先に紹介したデフォルトモード・ネットワークからセントラル・エグゼクティブ・ネットワークへの切り替えを行うネットワークを指しています。
サリエンス・ネットワークのアラートを出すことで、デフォルトモード・ネットワークと対極にあるセントラル・エグゼクティブ・ネットワークへと橋渡しをしてくれて、注意を向けられるようになります。
これは危機察知のときだけでなく、目立つものや、課題を解決してくれるもの、報酬価値の高いものも対象となります。
例えば、「通学路の途中で以前は空きテナントだったのに、そこに新しいショップができている」状況でも、「好奇心」という意味でサリエンス・ネットワークのアラートが出る場合があるのです。
集中力が持続しない理由
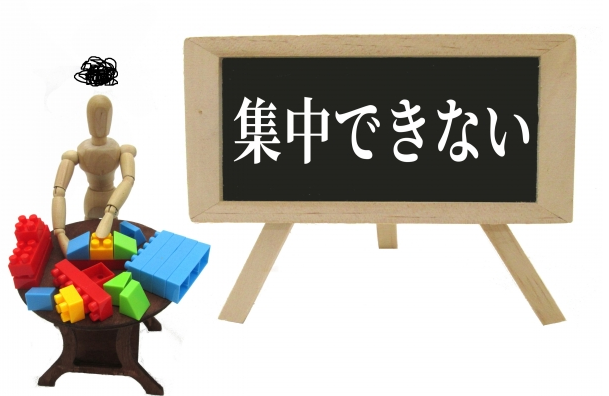
セントラル・エグゼクティブ・ネットワークが働き、ある物事に「集中して注意を向ける」状態でいるには、非常に多くのエネルギーが必要となり、脳への負荷が大きくなります。
すると、注意力は時間と共に散漫になってしまうので、結果的に集中力の持続もできなくなってしまうのです。
とはいえ、集中力が持続できないのは脳のしくみから仕方のないことであり、そもそも長時間集中すること自体に無理があるのです。
裏を返せば、短時間でも集中して学習した記憶はデフォルトモード・ネットワークとして自分の中に蓄積されます。いかにして、セントラル・エグゼクティブ・ネットワークの状態を増やすことができるかが集中力を持続させるために重要となるでしょう。
集中力を高めるには?
計画する・時間を区切る
では、勉強において集中力を高める・保つためにはどのような行動が必要でしょうか。
最初に必要なことは、目標を設定することです。
例えば、「次のテストで80点以上取ろう」と目標をもって勉強するのと、ただ漠然と勉強するのでは、学習時の集中力に大きく差が出ます。
目標設定をすることで、自分がやるべきことが整理され、目指すべきゴールに向かって集中することができます。
また、人間の集中力には「15・45・90の法則」があります。
深い集中が持続できるのはおよそ15分であり、子どもが集中力を保てる時間が45分、大人の限界が90分だそうです。
したがって、1日の朝から晩まで何時間も詰め込んでぶっ通しで勉強するのは避けた方がよいでしょう。
45分の勉強をしたら、5分~10分の休憩をはさみ、目を休めることが効果的です。
その際、あくまで“目を休める”ことが目的なので、スマホをいじったりするのはかえって目の負担を増やしてしまうことから休憩にはなりません。
タオルを目の上にあてて、何もせずにぼーっとしておくくらいの方が、脳にとっては良い休息になります。
環境と温度
環境を整えることも集中力に影響します。
「人は約70デシベル程度の適度な雑音がある方が作業効率や生産性が上がる」という研究結果があります。
学生がよく勉強場所として利用する図書館の雑音は約50デシベルに相当し、実際には静か過ぎて、些細な物音も気になってしまうようです。
約70デシベルに相当する環境は、身近なところだとカフェやレストランが当てはまります。
心理学の観点では一人で作業をするよりも、同様の作業をする人が傍にいることで刺激を受けやすくなり、達成効果も大きくなるようです。
他にも、室内の温度も重要なポイントです。
脳のしくみの一つに、「生命の危機や恐怖感をもったときの記憶が優先して思い起こされる」というものがあります。
そうすると、快適な温度が設定された環境より、少し寒いくらいの環境の方が記憶しやすいということになります。
具体的には23℃くらいがちょうど良く、気温が上がるごとにパフォーマンスは低下していくと言われています。
休憩する・香りや音楽…

アロマの香りを取り入れるのも、集中力の持続に効果があります。
アロマというとリラックスのイメージが強いのですが、香りの刺激は脳の海馬に直接刺激を加えることができるので、記憶定着の手助けとなります。
一般的に集中力を高めるのによく勧められているのはローズマリーやユーカリです。眠気を吹き飛ばしたいときはペパーミント、リフレッシュしたいときはレモンなどの柑橘系など、シチュエーションや自分の好みによって使い分けるのも良いでしょう。
音楽を聴くこともお勧めです。
自然音のもつ1/fゆらぎはリラックス効果を高めて、α波を脳から出してくれるのであなたの集中力を高めてくれます。
勉強中に聴くのであれば、BGMとしてクラシック音楽やジャズのインストゥルメンタルなどが適しており、YouTubeで検索してみると、さまざまなBGMを聴くことができます。
反面、ボーカルが入ってしまうと脳の思考と衝突してしまうため避けた方がよいでしょう。
ちなみに、「どうしても自分の好きな音楽を聴きたい!」と譲れない場合は、勉強の前に聴くことでモチベーションが上がってくるようです。
食べ物
食べ物の観点からも考えてみましょう。
集中力を高める食べ物として代表的なものは、ご飯・パン・麺類などの炭水化物です。
炭水化物を摂取することで、それらが体内で消化されたときにブドウ糖へと変化し体内の血糖値が上昇し、その間は集中力が高まるようです。
他にも、チョコレートはテオブロミンという成分が集中力を高めてくれるだけでなく、カカオの香りが自律神経を調節しリラックスさせてくれる効果も与えてくれます。
有名人に学ぶ、集中力の高め方
有名人はどうやって集中力をつけている?

世界で活躍する有名人は、どのような形で集中力を高めているのでしょうか。
例えば、長年テニスのATP(男子プロテニス協会)ツアーランキング1位に君臨しているノバク・ジョコビッチ選手はトレーニングの一環として「マインドフルネス」という瞑想を取り入れています。
コート内での厳しい戦いの最中では、ときには重要なサーブやバックハンドを失敗してしまい、精神的に慌ててしまったり、自分のプレーに不安を抱いたりすることがあるかもしれません。
ジョコビッチ選手はそんな瞬間に陥っても、マインドフルネスのトレーニングのおかげでネガティブな感情をそのまま受け入れることができるようになり、余計な雑念にとらわれることなく、目の前のテニスに全精力を注ぐことができるそうです。
他にもある!集中力の高め方
瞑想の他におススメなのは、将棋です。
日本将棋連盟がプロ棋士161人を対象に行ったアンケートによると、「将棋を始めて、1番変わったことは何か?」という質問に対し、約6割もの棋士が「一つの事を集中して考えられるようになった」と答えたそうです。
確かにプロ棋士の域になると、一つの手を指すたびに先の100手~1,000手ほどを読んでいくといいます。(ちなみに、プロ棋士は頭の中に将棋盤を思い浮かべることができ、実際に駒を動かすことがなくても正確に局面をイメージすることができるそうです。)
少しでも集中を欠いてしまったり、ほんの数手でも読み切れなかったりすると悪手を指してしまう可能性があり、プロレベルではその瞬間に勝敗が決してしまうこともあります。
そのため、棋士は常に正確に局面を読み、最善の一手を常に導き出さなくてはなりません。
対局中はこれを朝から晩までずっと続けるのですから、並外れたの集中力がないとプロ棋士は務まらないのです。
かの羽生善治九段は、『集中力は、人に教えてもらったり、聞いて身につくものではない。勝負どころでの集中力を発揮するには、集中できる環境を自らつくり出すことこそが大切だと思っている。』と語っています。
プロ棋士ほどとはいわないまでも、将棋に触れてみることで、集中力を高めるトレーニングになるのではないでしょうか。

まとめ
そもそも、“集中力が無い人”はいません。
好きなことや、興味があることに関しては自ずと集中していることが多いと思います。
それと同時に、人間は”自然と集中ができる生き物”でもないのです。
したがって大切なことは、「いかにして集中力を発揮できる状態を作り出せるか」ということです。
まずは、今回紹介した方法の中から自分がやりやすいものを選び、ルーティーンにできるよう実践してみましょう。
集中するためのルーティーンが確立したとき、きっと今よりも高い学習効果が得られるはずです。







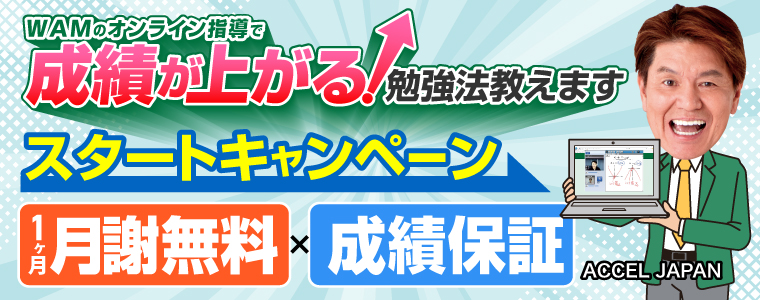

 0120-333-876
0120-333-876