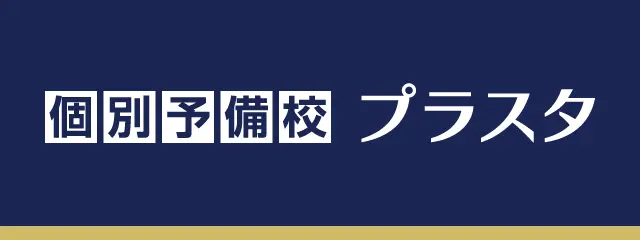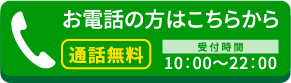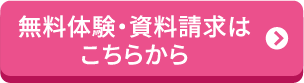成績アップにつながる中学社会の勉強法
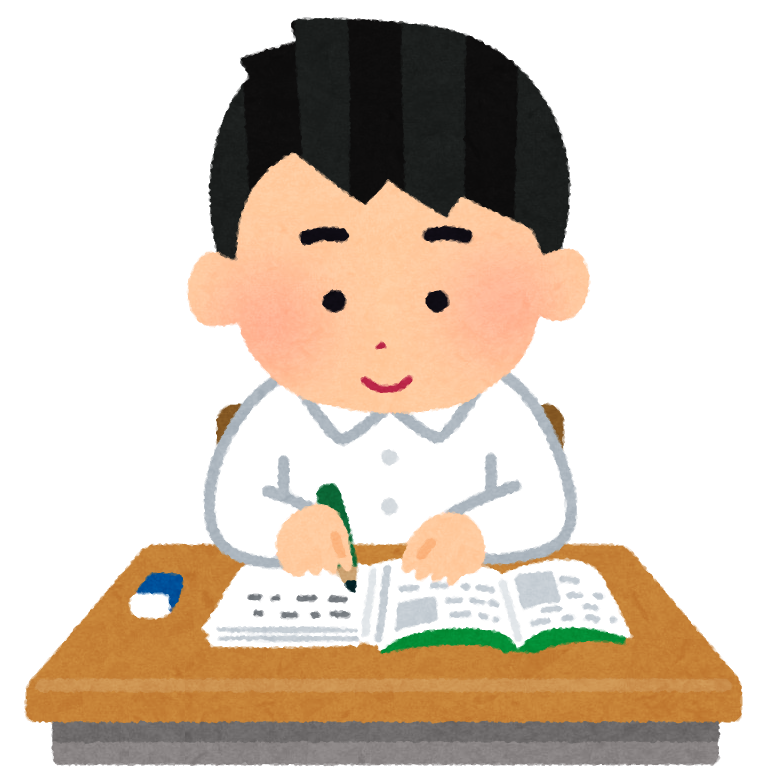
こんにちは!オンライン家庭教師WAMです(^^)/
「テストで点数を上げたい!」「通知表の成績を上げたい!」
という願いが叶うなら、皆さんもちろん叶えたいですよね。
でも、願うだけでは叶いません(涙)。
当然、勉強をしなければならないのですが、「手っ取り早く上がる教科はないかな?」と考えた時、まず思い浮かぶのは暗記系が多い教科ではないでしょうか。
今回は、特に暗記系が多い教科「社会」に注目したいと思います。
社会の勉強方法
社会が苦手な方へ
社会には、大きく分けて「地理」「歴史」「公民」の三分野があります。
私(筆者)が中学生の頃は、中1で地理を習い、中2で歴史を、中3の途中から公民を習うというスタイルでした。現在は、地理と歴史を一定期間で区切って交互に教える方法、あるいは完全に地理と歴史を別の授業にして、並行して教える方法をとる自治体が多いです。
いずれにせよ、3つの分野の勉強する事になるので、苦手な分野があると社会の成績で足を引っ張る可能性があります。
「地理が苦手だけど歴史は好き」とか、逆に「歴史は苦手だけど地理は好き」という人もいるでしょう。
それはつまり、苦手な方を頑張れば、得意科目に好転する可能性があるという事にもつながります。
では、社会が苦手な人は、どういう点に気を付ければいいのでしょうか。
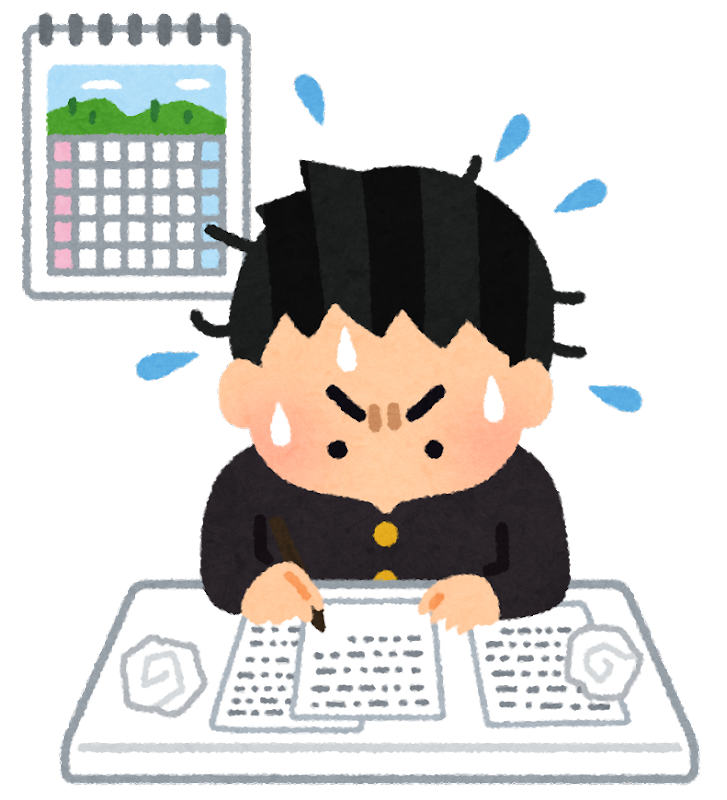
暗記だから…
最初に書いた通り、社会は暗記する事が多い科目です。
定期テストでも、問題数が一番多い科目が社会ではないでしょうか。
1問1点の100問テストになる事もあり、社会がいかに暗記して用語を書かせ、選択させる問題が多いかを物語っています。
では、覚える量が多いこの科目を、どうやって記憶に残すかが点数を伸ばすポイントになりそうですね。
授業で初めて聞いた語句は、後で覚えるために教科書に線を引いたり、メモ書きして残しておいたりして、できる限り授業後の早い段階で、改めて見直しをするだけでも、記憶に残りやすいです。
みなさんは、「エビングハウスの忘却曲線」をご存知でしょうか。
このワムノートで記事検索をかけても、既に5つの記事の中で出てくる、勉強の重要ワードです。
簡単に言うと「人は復習しないと、覚えたことを忘れる。できるだけ早く復習し、回数を多くしたほうが、記憶は定着しやすい」という事です。
暗記系だからこそ、後回しにせずすぐにするほうが、よい結果に繋がるという事です。
基本的な勉強法
暗記する事が多いからこそ、早い段階での復習を、と先ほども書きました。
できれば学校や塾で授業を受けた日に、その日の授業を振り返り、新しく出てきた語句は覚えるという事を繰り返してください。
いったん覚えたら、一問一答のような形でいいので、問題を解いてみましょう。
間違えた所は再び暗記です。
それができれば、テスト形式の問題演習で記述問題にも備えていきましょう。
インプット⇔アウトプットの繰り返しで、どんどん強化されていきます。
教科書や塾の教材、学校のワーク等、今手元にあるものでも、かなりの勉強はできます。
頑張ってください!
コツってあるの?
「地理」「歴史」「公民」の各分野で、暗記以外にも勉強のコツがあるのかをお話しします。
地理の勉強方法
地理は、世界地理と日本地理に分けられますが、基本的には国名や都市名、地名、各地域の気候や暮らし、産業や工業、独特な事などを勉強していきます。
世界地理では世界地図の種類や時差の問題、日本地理では地形図や縮尺比から距離を求める問題など、それぞれに独特な問題があります。
世界地理と日本地理で、どちらかが不得意という生徒さんもいるかと思います。
世界地理の場合、カタカナが多くなり混乱するという点、日本地理の場合、漢字を苦手としている点が挙げられます。各用語は暗記しなければならないので、一問一答形式のような演習を繰り返し、覚えていきましょう。
その他で入試でもよく出題されるのが、時差の問題や気温・降水量から気候を読み取る問題です。
時差に関しては、イギリスのロンドンにあるグリニッジ天文台を、南北に本初子午線が通り、そこを基準に東に15度進むと1時間早くなり、西に15度進むと1時間遅くなるというルールを覚えましょう。そして180度分進むと、日付変更線があり、東にまたぐと1日遅く、西にまたぐと1日早くなります。特に覚えないといけない事は、日本は東経135度の経線が国土を通過しているので、135÷15=9時間イギリスより早いという事です。
時差の問題も、考え方をマスターすれば、得意分野に化けてくれるでしょう。
気候に関しては、世界で10区分、日本国内で6区分に分けられます。それぞれポイントとなるのは、年間降水量や月別の降水量、年平均気温と月平均気温です。これらを見ることで、特徴をとらえてどの区分になるのか、演習を重ねてください。
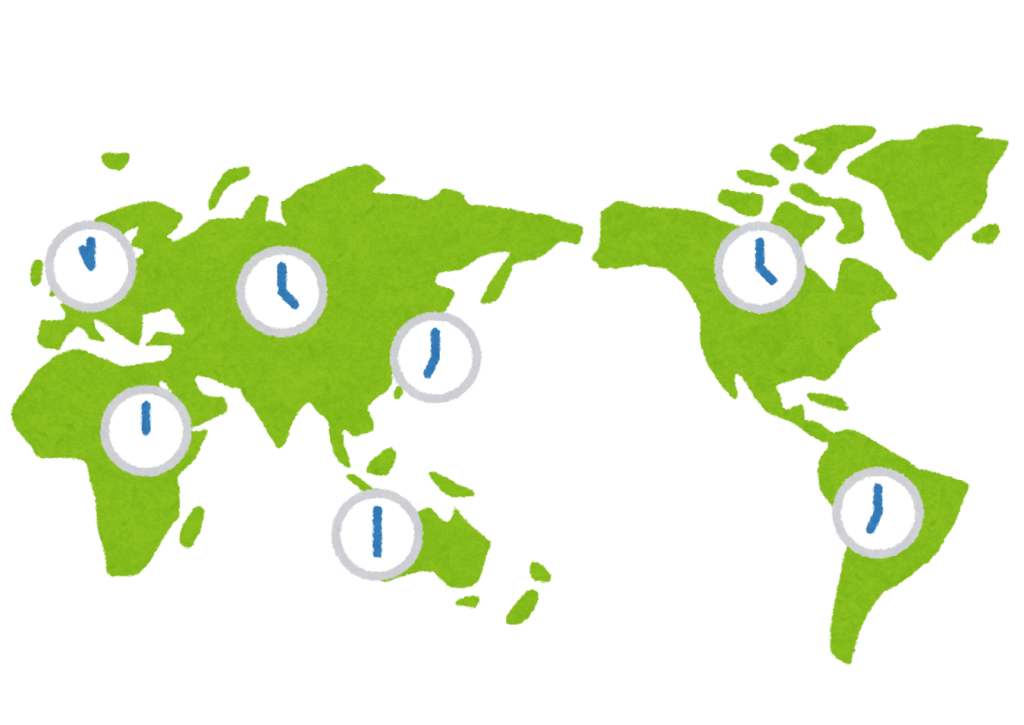
歴史の勉強方法
歴史に関しても、高校で言う「世界史」と「日本史」に分けられますが、地理ほど平等には扱わず、日本の歴史が大部分を占めます。
そして歴史は、学術的に史料や文献をたどって研究する事になりますので、昔よりも現代に近いほうが、その史料や文献も多く残っています。つまり、今に近いほど勉強する事が多い分野になりますので、歴史の中間折り返し点は、江戸幕府の幕末あたりだと思ってください。
そして、歴史を苦手にしている生徒さんには、西暦何年に何が起きたという「何年」が覚えられないと言う人が多いです。
確かに数字を覚える事って、難しいですよね。
歴史的な事に関しては、なぜそうなったのかという時代背景があります。それを正確に捉えられているか、が問題なのですが「わざわざ何年まで覚える必要ってあるの??」と思われる人もいるでしょう。そんな時は、古典的ですが「語呂合わせ」で覚えるのはどうでしょうか。
例えば、「平安京と平城京、どちらが先に建てられたか」という問題も
・なんと(710)立派な平城京
・鳴くよ(794)ウグイス平安京
という風に、年代のヒントになる言葉を組み込んで覚える方法です。
口で何度か暗唱すると覚えられますので、方法の1つとして使ってみて下さい。
別の方法として、「漫画を読んで覚える」という方法も、昔からよく採用されています。
学校の図書館で、一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。学習まんが「日本の歴史」などを、繰り返し読む事で歴史を覚える方法です。漫画でストーリー仕立てになっているので、読みやすく取り掛かりやすいのが特徴です。自分で全巻そろえようと思うと・・・結構な額になるので、図書館の利用をおすすめします。

公民の勉強方法
最後に、公民についてです。学校により多少前後しますが、歴史の授業は、中学3年生の1学期中に終わります。
歴史の最後は、今いる社会に非常に近い過去の話で、そこから今現在の身の回りは、どのような社会になっているのかを勉強していく事になります。
公民の内容は、実生活で非常に話題になりやすいものです。
例えば、現在では18歳で選挙権が得られますから、公民の授業を受けて3年後には大小様々な自治体の選挙に参加する事ができます。選挙で立候補するには、もう少し年齢が高くなりますが、国会や自治体の行政、法律ができるまで等、ニュースでも取り上げられるような内容が中心です。
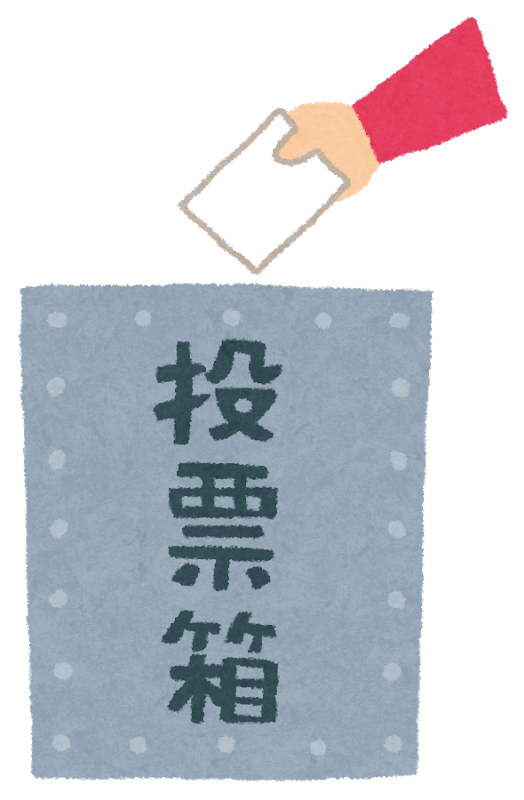
法律や憲法、経済や裁判、社会問題も多く取り上げられますが、注意しておきたい事は「数字を覚える所が意外と多く、間違えやすい」という事です。
例えば、「この一文は日本国憲法の何条か」「衆議院の定員は何名か」「参議院の任期は何年か」「裁判員裁判で、裁判員は何名が選ばれるか」などです。
これらは一度、問題を解いて頭で整理する事が、覚えるためのポイントです。
公民分野に関しても、基礎的な問題は何度か繰り返して演習しましょう。
まとめ
地理、歴史、公民と3つの分野で構成されている中学社会ですが、高校入試となると、それぞれの分野が混ざった「融合問題」という形が出題されやすいです。
特に「地理歴史融合問題」は多く出てきて、いきなり解こうとするとなかなか難しいです。基礎的な演習で各分野を覚えたら、融合問題にもチャレンジしていきましょう。
また、近年増える傾向にあるのが「SDGsを含んだ問題」です。
環境と地理、歴史、公民は非常につながりのある分野ですので、見つけた場合は要チェックですね!







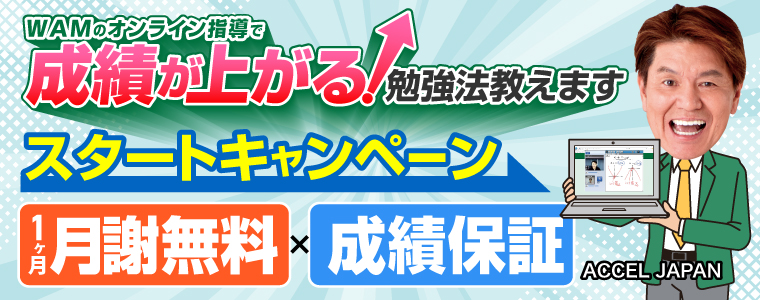

 0120-333-876
0120-333-876